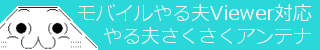“じっと耐える”人たちの尊さを知った――尾崎世界観がコロナ禍の中に見たもの

多くの人は、ロックバンド・クリープハイプのフロントマンとして、彼のことを認識しているだろう。だが、そのパブリックイメージに「作家」という肩書きが加わって久しい。
とくに、新作『母影』(新潮社)が第164回芥川賞候補作にノミネートされて以降は、改めてその存在や発言に注目が集まっている。
だが、そんな世間の視線をよそに、彼はこう言う――「何かをした人より、“何もせずにじっと耐える”人にもっと目を向けたい」と。
圧倒的な情報量に埋没させられそうな今の世の中で、なぜ彼は“じっと耐える”ことの尊さに想いを馳せたのか。
『母影』のこと。クリープハイプのメンバーのこと。そして、新型コロナウイルスによって変わってしまったこの世の中で考えたこと。尾崎世界観の想いを、約1万2,000字のロングインタビューに綴じ込めた。
ヘアメイク/谷本慧

ちゃんと小説で批評をされたいという気持ちがあった
- 初の文芸誌掲載作品『母影』(新潮社)が第164回芥川龍之介賞候補作に選出されました。残念ながら受賞には至りませんでしたが(※取材が行われたのは2月上旬)、ノミネートされたときの気持ちを改めて聞かせていただけますか。
- うれしいなというのが素直な感想でした。
音楽活動にはなかなか明確な結果がないので。勝ち負けがないのがよさかもしれないけれど、物足りないというか、メジャーデビューから10年近くやってきて、何か結果が欲しいという気持ちもあったんです。 - それは他者からの評価が欲しいということですか。
- 音楽活動では、他者の言葉はそんなに気にならないんです。自分がリスナーの立場でも、誰かにこの曲よくないよねと言われたって、自分がいいと思っていたらそれでいいんです。
- 自分の中に揺るぎない音楽観があるから、とくに影響を受けないと。
- そうですね。低反発のマットレスみたいなものです(笑)。自分という人間に過不足なく当てはまるというか、ちゃんと自分の体に添ってくれる感じが、音楽にはある。
でも小説は違うんです。自分の形にはなってくれない。むしろ、どうにかして自分がその形になっていくようなイメージです。
だから小説を書いているときは、他者からの目がすごく気になる。小説にはまだ批評の文化があるので、自分自身、誰かの批評を読む機会も多いし、自分がいいと思った作品でも他者の批評を読むことで評価が覆ったりします。
そういう、何かをひっくり返す力が小説の批評にはあると思っていて。だから今回の『母影』は、まず批評をされたいという気持ちがすごく強かったんです。 - それだけ批評を欲していたのは、なぜなんでしょうか。
- 2016年に『祐介』という小説を書いたとき、書店に行ってもタレント本コーナーにしか置かれていなかったのがすごく悔しかったんです。手に取ってくれる人はいたんですけど、ただ形態を変えただけで、CDの延長でしかない気がして、本として届けきれなかった。
小説を書くというのは音楽とはまったくベクトルが違うし、自分の中では途方もない作業だったんですけど、結局は通じないんだという壁にぶつかって、ずっともがいていました。
今回の『母影』が芥川賞にノミネートされたことで、あのときの壁を少しでも超えられたのかなという気がして、うれしかったですね。 - ミュージシャンである自分が、文壇界に認められたような感覚ですか。
- 認めてもらえたとは思っていません。でも、入り口がどこにあるかわかったという感じですね。
最初はどこから入っていいのかわからなくて。というか、ドアがあるのかどうかすらわからなかったんですけど(笑)。今回のノミネートで、ここにドアがあるとわかった。まだ入れてはいないけれど、いつかちゃんと中に入れるように、今後も書き続けたいです。

小説を書くことは、音楽からの逃げ道だった
- 執筆期間はどれくらいだったんですか。
- 1年くらいです。前から、なんとなく書いてはいました。本格的に書き始めたのは昨年の緊急事態宣言以降ですね。ライブができない中で、考える時間がすごく多くて。
- 本来ならクリープハイプは、2020年に10周年記念ツアーを敢行する予定でした。
- ツアー最大規模の会場で、チケットも売り切れていて。ちゃんと期待値を感じながらそこに向かっていたので、中止が決まったときは、仕方のないことなんですけど、どうしていいかわからない気持ちでした。配信シングルを出したりもしたんですけど、どうにもその流れに気持ちが乗っていかなかった。
その中で、自分がバンドに返せるものはこれしかない、そんな気持ちで書き上げたのが『母影』だったんです。
もともと自分にとって、小説は音楽がうまくできないときの逃げ道だったんですね。 - デビュー作の『祐介』を書いたときもそうおっしゃっていましたね。
- そうです。今もずっとそうなんですけど、体の不調で歌がうまく歌えなくなって、そのときに小説を書いたことで救われたんです。
今回もそう。ライブができない中で、音楽を黙々と作り続けることもできた。でもライブができないから曲を作ろうという選択は、自分の中でコロナに負けたような感じがして嫌だったんです。小説を書くことは、音楽がうまくできない自分に対する逃げ道でした。
悔しい思いをしてきた2020年に、1発殴り返せた
- 小説を書いている時間は、クリープハイプのメンバーであるという意識から切り離されている感じなのでしょうか。
- 切り離していたと思うんですけど、そのぶん意識しているというか。出稼ぎに行っている感じですね(笑)。必ず最後はクリープハイプに持って帰るという意識がありました。
文芸誌は特殊で、向こうから執筆の依頼が来たとしても、いいものを書けなかったら「今回はちょっと……」と掲載を見送られるんです。他の業界では、こんなことはないですよね。 - たしかに。ただ、見合うものでなければそうやってボツにすることで、文芸誌の質が保たれているんだろうなと思います。
- だから『母影』が『新潮』に載ったときは、すごくうれしかったんです。そこに、今度は芥川賞ノミネートの知らせがきて。ハードルが高いことはもちろんわかっていたんですけど、悔しい思いをしてきたこの1年に、最後に何か1発殴り返してやれたという気がしました。
個人としても、バンドとしても、これでどうにか2020年を終われるなという気持ちがありました。 - 小説を書く作業は、音楽と比べても孤独ですか。
- そうですね。音楽に孤独な感じはないので。
- それは、バンドのメンバーがいるから?
- 物理的にもそうだし、僕の中で音楽は、“待つ”感じなんですよ。昨日もレコーディングだったんですけど、歌詞が書ききれなくて、明日のボーカルレコーディングまでになんとか書き上げなきゃと思いながら、今もこのインタビューに答えています(笑)。
- 大変お忙しい中、恐縮です(笑)。
- (笑)。でも、それも“待つ”感じなんですよね。状況だけ考えれば、締め切りがどんどん近づいているんですけど、それも「書く」というより“待つ”行為なんです。
- 自分の中で熟してくるのを“待つ”ような?
- 出てくるのを“待つ”という感じです。
でも、小説はそれが一切ない。待って出てくることはないから、自分から動いていかなきゃいけない。向こうから来る感じがないんです。そういう意味でも孤独でした。
本当にスゴいのは、“じっと耐えて”待ってくれた3人です
- そうした孤独の中で、メンバー(小川幸慈さん、長谷川カオナシさん、小泉拓さん)の支えを感じることはありましたか。
- 曲を作るときもそうなんですけど、メンバーに対しては常に「スゴい」と思わせたい気持ちがあるので、悩んでいることとかを言わないんです。
- じゃあ『母影』の執筆期間中に、原稿を先に読んでもらったりすることも?
- まったくなかったですね。完成したものをそれぞれ読んでくれて、前回の『祐介』よりも深い感想をもらえたので、そこで何か今までと違うものを書けたという実感を得ることができました。
- Twitterでは、芥川賞の候補に選出された際に「今回の芥川賞候補を、メンバー三人に捧げます。」とつぶやかれていました。
芥川賞候補だ!嬉しい!
— 尾崎世界観 (@ozakisekaikan) December 17, 2020
小説を書く時間をくれたメンバーに感謝しているし、今回の芥川賞候補を、メンバー三人に捧げます。いつも恥ずかしくて言えないけど、ありがとう!やったぞ!これからもよろしく!- 候補に選ばれたとき、メンバーがすごく喜んでくれたんですよ。
自分が逆の立場だったら、悔しい面もあると思うんです。バンド活動ができない中で、ボーカルだけが執筆活動をして。緊急事態宣言で音楽ができなくなったとき、自分は今まで書きものをやってきたことに救われたけれど、他のメンバーはただ何もできない時間だけが増えた。
ああいう状況下で、“何もしない”ってすごく難しいと思うんですね。 - とくに去年のステイホーム期間は、すごくそれを感じました。
- そうなんです。“何もしない”というのは相当な努力が必要だし、かなりの負荷がかかっている。他のバンドを見ても、いろんな人がいろんなことを始めていて。それはすごくわかるし、そういうことをしないと自分を保っていられなかったんだと思うんですよ、きっと。
“何もしない”というのは、精神的に本当につらいこと。でも、メンバーはそれを我慢してやってくれた。何もしないということは、これまで作ってきたバンドのイメージを新型コロナから守ることでもあります。世間は芥川賞の候補になったというニュースだけを見て、尾崎世界観が何かしたんだと思ってくれるかもしれないけれど、本当にスゴいのは“何もしない”で待った3人なんです。
だから、あのとき「今回の芥川賞候補を、メンバー三人に捧げます」とつぶやきました。本当は芥川賞を捧げたかったんですけどね。それは、次の目標として追い続けたいです。

感情と体がうまく連動しない苦しみを小説に結びつけたい
- 『母影』は、母親が勤めるマッサージ店の片隅で、接客している母の姿をカーテン越しにこっそりと見ている小学生の女の子が主人公です。よく行く整体マッサージで小学生の女の子が宿題をしている場面に遭遇したことが着想のキッカケだとおっしゃっていましたが、その女の子に創作意欲が刺激されたのはなぜなんでしょう。
- 自分自身、大人のことをよく見ている子どもで。大人特有の、子どもに対してわざと視点を落として接するあの不気味さやいやらしさを、当時から冷静に受け取っていたんです。
だから、今でも友達の子どもに接するときに、なんてしゃべっていいのかがわからない。タメ口が嫌だから、敬語でしゃべりたくなるんですけど、それもおかしいし(笑)。 - 変に猫撫で声になっている自分が気持ち悪かったりしますよね。
- そうなんです。甥っ子と接する機会も増えて多少は慣れたけれど、それでもいちばん接しづらい相手ですね。まずはそんな、自分が子どもだった頃の視点も含めて書いてみたいという気持ちがありました。
あと、言葉には、相手とやりとりをしているうちになんとなくお互いのあいだでちょうどいいサイズに収まってしまうような印象があります。 本当はちょっと違うんだけど、ひとまずこの言葉を当てはめておこう、というような。 - わかります(笑)。
- でも、子どもは一方的に受信するだけで発信ができないから、折り合いをつける必要がない。そのぶん、気持ちの鮮度が高いと思っていて。そんな子どもの視点で書くことで、言葉になる以前の何かを言葉で表したいという気持ちがありました。
- それをやりたいと思ったのはなぜなんでしょう。
- さっき話した、体をうまく使えなくて歌が歌いづらいという悩みが大きいと思います。こういう言い方をしてはいけないけれど、新型コロナでライブがなくなったとき、ちょっとホッとしたんです。もうあんな苦しい思いや恥ずかしい思いをしなくていいんだって。
自分の感情と体がうまく連動しない。この苦しみを小説に結びつけたいと思って、言葉は知らないけれど感覚だけはわかる、そんな子どもの視点に行き着いたんです。 - 『母影』の「私は書けないけど読めた――お母さんの秘密を」というコピーが、まさにその連動しない感覚と符合しますね。
- そうですね。頭ではこういうふうに歌いたいと明確に思っているのに、うまく体が使えなくて。それが本当に情けないんですよね。
- 小学生の女の子という設定は、今の尾崎さんとはまるで重ならないキャラクターですけど、ある意味で幹の部分は、尾崎さんの今の苦しみがそのまま反映されているんですね。
- 思い通りにいかない、核心に触れられないというのは、常に思っていることです。でもその苦しさがあるから、今もこうして活動を続けられているのかもしれません。
体をうまく使えなくなったことで、一生懸命ケアをするようになったし、ライブに対する気持ちも強くなった。不思議ですね。たとえ不幸や不自由な状況だったとしても、必ずしもそれが本当に悪いことかどうかはわからない、身をもってそう感じています。

子どもの頃の感覚を、どういう言葉で言い表せられるか
- 『母影』を読んでいて唸ったのは、小学生の女の子の心理描写です。「グーで勝つと謝りたくなる」とか、「硬貨の中で100円玉が好き」とか、たしかにあの頃感じた、でも大人になった今はすっかり忘れてしまっていた感覚が鮮やかに綴られていて。尾崎さんはどうしてこんなに解像度高くあの頃の気持ちを思い出せるんだろうと驚きました。
- まず自分にできるところが、そこしかなかったんです。小説を書くうえでのルールを知らずに書き始めたので。
- それは、今でもあの頃の感覚が自分の中に残っているという感じですか。
- いや、かなり引っ張り出してきていますね。そこは作詞に近いかもしれないです。この感覚をどういう言葉で言い表せるか。たとえ世の中ですでに言い方が成立している感覚でも、こういうふうに言い換えることができるんじゃないかと探っていく。それはものすごく大変な作業なんですけど。
でも、こういう感覚ってあったよなというものを見つけられると、まだ書いてもいいんだと許しをもらった気持ちになる。昔、オーディション系の歌番組で、審査員がボタンを押すと歌える時間が延びるというのがあったじゃないですか。ああいう感じです(笑)。
自分の中で、それまでうまく言葉にできなかった感覚を見つけるたびに、まだ自分はやれるんだって思っていました。 - 小学生だった自分に会いに行くという感覚でもない?
- 会いに行くという感覚ではないですね。でも、実際にあったエピソードを引っ張り出したりはしています。
途中で、主人公の女の子が徘徊しているおじいちゃんを「欲しい」と言う場面があるんですけど、実際、小学生のとき近所にすごく優しくしてくれたおじいちゃんがいて、この人が友達だったらいいなと思ったことがあったんです。
でもそうやって一緒にいたら、そのおじいちゃんの家族らしき人が「早く帰るよ!」って怒りながら、おじいちゃんを引っ張っていったんです。今思えば、あのおじいちゃんはボケてしまっていて、こっそり家を抜け出して徘徊していたのかもしれません。
そのおじいちゃんと過ごした夕方の感じをよく覚えていて、そういう幼少期の記憶が活きているところはあります。
子どもとして純粋に過ごせなかった苦しさがあった
- 「無邪気」や「甘酸っぱい」など、いろんな単語で形容されることの多い小学生時代。尾崎さんの言葉で表現すると、自身の小学生時代はどんなものでしたか。
- 早く飛ばしたかったですね。YouTubeを観ていると広告が出てくるじゃないですか。あれです(笑)。早く飛ばしたくてしょうがなくて、ずっと右下を押している感じ(笑)。
友達と遊んでいても面白くないし、友達の家に行っても居心地が悪い。どうしても無邪気になれなかったんです。
自分が遊びに来たことを、この家の大人たちはどう思っているんだろうとか。「このあと、ご飯どうするの?」って大人たちが話しているのが聞こえてくるんですよ。それを聞きながら、これは自分のことを言っているのかな、でも別にご飯が食べたいから来たわけじゃないし、こっちもこっちで気をつかうのになと思っていて。 - めちゃくちゃわかります。
- 『母影』の中に出てくる「ちょっとだけ知っている人のご飯が気持ち悪いのはどうしてだろう」という1文は、まさに当時の自分が思っていたことです。当時はそう思うことで、大人に対してこっちにも意地があるんだぞという反抗の意思を示したかったのかもしれません。
子どもとして純粋に過ごせなかった苦しさがあって、その苦しさが幼少期から今までずっと地続きでつながっている気がします。 - タイトルの『母影』は最初からイメージしていましたか。それとも最後につけましたか。
- タイトルは最初からなんとなく考えていました。マッサージ店では、カーテンの向こう側にいるお母さんを絶対に見ないと最初から決めていたので。じゃあ、どうすればお母さんが何をしているのかわかるかを考えたら、“影”に行き着いたんです。
カーテン越しにどう影が見えるかについては、よく夜中に自分の家のカーテンで、こうやって光を当てながら実験していました(と、身振り手振りで実演する)。どう見ても怪しいやつですけど(笑)。

人に嫌いだと言われるのが、自分のいいところでもある
- クリエイターの本音という意味で聞きたいんですけど、自分の書いた小説が共感されるのってうれしいですか。
- うれしいです。間違っていなかったんだなと思えるので。そのぶん、すごく嫌悪を示されることも多いんですけど。全員に褒められたらうれしいだろうけど、人に嫌いだと言われるのが、自分のいいところでもあると思うので。
でも難しいですね。せめて好き嫌いの割合が8:2か、7:3になってほしいんですけど。5:5っていうのは……(笑)。 - 5:5なんですね(笑)。
- 5:5です(笑)。
- 相手にわかってもらいたい気持ちはありますか。
- 変な感覚を持っているというのはよく周りからも言われるし、それを武器にやっているので、そこをわかってもらえるとうれしいです。
- 最近、とくにコンテンツに関しては、共感できるかどうかが第一になっている気がして。それがどうなんだろうと思う面もあります。
- そうですね。とくに最近は、消費されるスピードが速くなっていますね。作品を作るときも、質よりも先に「速くわかるものじゃないといけない」というのがある気がします。
小説のレビューサイトでも「よくわかりませんでした」という意見を見るんですけど、それで終わっていいのかなと引っかかります。わざわざレビューサイトに書き込むほどの気持ちがあるのに、「私にはよくわかりませんでした」で終わるその気持ちが自分にはわからない。
あと、批判を書くとき、わざわざ「ごめんなさい」って謝るのは何なんでしょうか。 - (笑)。ありますね。
- 僕は批判される側なのでこの意見は読者の方にあまり共感されないと思うんですけど、わざわざ「ごめんなさい」と謝ってから批判するのは、図々しいというか、すごく傲慢さを感じるんです。否定するものに謝るのは矛盾しているし、感情の無駄使いだと思います。
大声で言い合うことは、中間にいる人を苦しめることになる
- SNSが普及して、誰もが発信できる時代になって。いろんな声が可視化されるようになったぶん、モヤモヤを感じることも増えました。
- とくに今は世の中がどんどん変わっていっているタイミングで、それに対していろんな意見が出てくるじゃないですか。そういった中で、声のデカい人がいて、その人の意見に反対の意見をあげようとすると、そっちも声を大きくするしかないから、結局その中間にいる人がどうしようもなくなる。
- わかる気がします。言っていることはすごく正しいし、自分も声をあげて世の中を変えていかなきゃと思いもするけれど、大きな声で言い合っている人を見ていると、すごくしんどくなります。
- まさに自分がそうなんですけど、変わらなきゃと思い始めている人、でもまだまだ変わりきれていなくてそこにコンプレックスを持っている人に、そういった大きい声がいちばん刺さってしまう。そして、それが結果として、今から変わっていこうという人の意志を摘み取っている気がします。
もちろん大きな声をあげている人も、今まで普通の声で言っても世の中が変わらなかったから大声を出しているはずで、その気持ちはすごくわかるんです。
だけど、大声で怒鳴らなきゃ聞こえない相手じゃなくて、まずは普通にしゃべって聞こえる相手に伝えていくのが大事なんじゃないかと思うんです。
今のニュースは称賛と批判のどっちかで、中間がない
- 大きい声だけが、世の中の声ではない。黙っている人もそれぞれいろんなことを考えていることは意識しておきたいですね。
- 『母影』の「ないけど、ある」ですね。
今はなんでも極端ですよね。それこそライブドアニュースでも、テレビで誰かが言ったことに対する「〜〜に称賛の声」という記事がよく出てきますけど(笑)。 - 「〜〜に批判の声」とか(笑)。
- 常に称賛か批判のどっちかですよね。その中間がない。
- クリックされるように、そういう見出しを使うメディアにも問題があると思います。
- でも、こうやってエラそうに言っている自分もつい見ちゃう……。ライブドアニュースって、クリックした記事のタイトルが紫色に変わるじゃないですか。いつも紫ばっかりですから……(笑)。
そういう矛盾したところがあるんですよね。人が堕ちていくところを見たいし、人が上がっていくところも見たくはないけれど、やっぱり気になって見てしまう。
でも今は、批判記事よりも、称賛記事に違和感を覚えますね。 - えっ。批判より称賛にですか。
- 単純な嫉妬心もあると思うんですけど、何か正しさを押しつけられている気がして。ああいう記事をいっぱい見ていると、楽じゃないですか。こういう発言をしたら称賛されるんだっていう、今の世の中の空気がわかるから。
でも不意に怖くなります、そうやって称賛されている人がいつか……と。

常に目標と悔しさが影みたいにくっついている
- Twitterの更新は停止されていますが、やっぱりご覧になっているんですよね。
- 見ています。やめられないですね。違法なことじゃない限り、別にやめなくてもいいと思うんですけど、本当に疲れます。エゴサーチをして、何でこんな悪意ばかり吸収しちゃうんだろうって思うんですけど。
- SNS疲れを感じながらも離れられない人は、今の世の中、大勢いますしね。
- 離れなくていいと思いますけどね。だいたい生きていること自体、疲れることですよね。それに、疲れるほどやってしまうことは、やっぱり自分に必要なことなんじゃないかと思います。
自分もそうやっていろんな悪意を吸収しながら、結局こうして話したり、表現のネタにしているので。 - 尾崎さんはよく「怒りが表現の原動力」とおっしゃっていますが、年をとるごとに怒り続けるのって疲れませんか? これは個人的な意見なんですが、なんだか怒りって自分を傷めつけているようなところがあって、それだけではずっと走っていけないなと年をとるほど感じます。
- そうですね。疲れるというのもわかります。実際、年を重ねて状況が変わっていくにつれ、丸くなったと言われることも増えました。
ただそうやって広い世界を知るたびに、怒りの種類も変わってくるんです。 - 怒りの種類?
- 今の自分は周りからすると、満たされているように見えるようです。「こんなにいい状態で何が不満なんですか?」と。でも、何も変わっていないんですよね。
アマチュアのときはライブをしても会場が埋まらなくて、チケットノルマばかりを払わされて悔しい思いをしていた。メジャーデビューしたらしたで、もっと上にいろんな人がいて、その人たちにかなわないことが悔しかった。結局、小さいライブハウスでお金を払ってライブをやっていた頃の自分と同じなんですよね。それは、その場所に応じた目標設定がちゃんとできているからこそだと思うんですけど。 - ああ、そうか。立つ場所によって、別の怒りがありますよね。
- 今回の芥川賞も、ノミネートはされたけれど結果はボロ負け。酷評されている記事を見て、「あー、恥ずかしい!」ってなるし。だから、ずっと同じなんです。
でも、そういう感覚を持っていられて幸せだと思います。常に目標と悔しさが影みたいにくっついている今の状態がいいのかもしれませんね。
“じっと耐える”人たちにもっと目が向く世の中に
- 最後に、コロナ禍について考えたことを聞かせてください。アーティストとしてこの状況下でどんなことを考えましたか。
- ウイルスという目に見えないものに怯える生活の中で、目に見えないものをちゃんと考えたいし、受け止めたいと改めて思うようになりました。
最初のほうで話したメンバーのこともそうですが、下手に動かず“じっと耐える”ことがどれほど大変で尊いことか。どうしても、何か行動をした人が批判されたり称賛されたりするけれど、そうじゃなくて、“じっと耐える”人に対してもう少し目を向けるのが大事なんじゃないかと思っています。 - たしかに。ただ粛々と行動を制限し、生活をしている人にはなかなかスポットが当たりません。
- 難しいですよね。でも自分が小説を書いたことで、じっと耐えていたメンバーに対して気づきがあったように、自分が何か行動を起こすときに、そうじゃない人をもう少しリスペクトできるような考えが広まっていったら、もっと生活しやすくなるのかもしれませんね。

10代の人たちを残念とかかわいそうとは言いたくない
- 別のインタビューで、2011年の震災のときはまだ無名で、音楽雑誌でミュージシャンたちがメッセージを送っているその中に名を連ねられなかったことが悔しかったとおっしゃっているのを読みました。今回は、もうすでに影響力を持っている立場として、何か発信したいと考えましたか。
- すごく考えたけれど、やっぱり答えは出ないですね。もう、そうやって迷いながら音楽活動をしていること自体が答えだと思っています。
さっきの大声の話にもつながるけれど、この状況下でクリープハイプがそんなに目立った活動をしていない、声をあげていないということ自体が、ひとつの結果にもうなっている。 - 有名なミュージシャンがメッセージを出して、それがSNS上で拡散される一方で、無言の人たちが何も考えていないわけではない。
- 『母影』も、ない声を拾うというのがひとつのテーマでした。そこに目が向いたのも、コロナ禍で改めて“無言の”人たちについて考えたからだと思います。聞こえてくる声だけでなく、そうした無言に耳を傾けられる人間でありたいです。
- 音楽などのエンターテインメントが“不要不急”と言われることに関しては、どう思いましたか。
- そう言われてしまうものなんだと、落ち込みました。でもたしかに不要不急だと思うし、それは仕方がないと思います。
何か大きな出来事があったときに、不要不急と言われるようなことを自分たちはやっている。その意識の上で、どう作品を届けていくか。
このコロナ禍で、音楽業界のシステムは変わっていくと思います。CDを出して、ツアーで各地を回って、またレコーディングをして、プロモーションをして……そんな既存のシステムとは別のシステムがまた作られていくはずです。その過程に、クリープハイプというバンドもちゃんと存在してたいですね。 - クリープハイプのリスナーには、10代の方も多いと思います。部活動や修学旅行、卒業式や成人式といったイベントもコロナ禍によって奪われました。尾崎さんから、そんな10代の人たちに向けて届けたい言葉はありますか。
- 当事者ではない自分が、「かわいそう」とか「残念」と言うのもおこがましいと思っています。
そうやって報道されると、本人たちも自分たちはかわいそうなんだと思ってしまうだろうし。でも、実際に残念だと思っている人も大勢いて、その人たちのことを思うといたたまれない気持ちになります。
ただ、それぞれにその時代の生き方があるように、いつかきっと“そういうもの”になっていくんだと思います。今10代の人たちも“そういうもの”を経て、何かまた新しいものを生み出していくはずです。
そして、いつか何か大きい出来事が起きたときに、“そういうもの”を経験した人たちだからこそかけてあげられる言葉があるはずです。だから、すごく大事な人たちだと思います。 - 尾崎さん自身は、このコロナ禍にどんな影響を与えられたと思いますか。
- まだこの状況は続くかもしれないし様子を見ながらですけど、今回のことが何かになったらいいではなく、何かにしないとダメだという強い意思を持って、しっかりやっていきたいです。
- 尾崎世界観(おざき・せかいかん)
- 1984年11月9日生まれ。東京都出身。O型。
2001年、クリープハイプを結成。2012年、1stアルバム『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』でメジャーデビューを果たす。同年、1stシングル『おやすみ泣き声、さよなら歌姫』を発売。週間オリコンチャートで初登場7位にランクインする。2016年、初小説『祐介』(文藝春秋)を書き下ろしで刊行。その他の著書に『苦汁100%』(文藝春秋)、『苦汁200%』(文藝春秋)、『泣きたくなるほど嬉しい日々に』(KADOKAWA)。対談集に『身のある話と、歯に詰まるワタシ』(朝日新聞社)があり、最新作『母影』(新潮社)は第164回芥川賞候補作にも選出された。2020年7月より、『セブンルール』(関西テレビ)にレギュラー出演。2021年4月からは弾き語りツアー「尾崎世界観の日 全国ツアー」を開催予定。
書籍情報
- 『母影』 著:尾崎世界観
サイン入り色紙プレゼント
今回インタビューをさせていただいた、尾崎世界観さんのサイン入り色紙を抽選で1名様にプレゼント。ご希望の方は、下記の項目をご確認いただいたうえ、奮ってご応募ください。
- 応募方法
- ライブドアニュースのTwitterアカウント(@livedoornews)をフォロー&以下のツイートをRT
\小説『#母影』発売中!/#クリープハイプ #尾崎世界観 サイン入り色紙を1名様にプレゼント!
— ライブドアニュース (@livedoornews) March 9, 2021
・フォロー&RTで応募完了
・応募〆切は3/15(月)18:00
インタビューはこちら▼https://t.co/OS4uMFlTN2 pic.twitter.com/r9zVTUMgOo- 受付期間
- 2020年3月9日(火)18:00〜3月15日(月)18:00
- 当選者確定フロー
- 当選者発表日/3月16日(火)
- 当選者発表方法/応募受付終了後、厳正なる抽選を行い、個人情報の安全な受け渡しのため、運営スタッフから個別にご連絡をさせていただく形で発表とさせていただきます。
- 当選者発表後の流れ/当選者様にはライブドアニュース運営スタッフから3月16日(火)中に、ダイレクトメッセージでご連絡させていただき3月19日(金)までに当選者様からのお返事が確認できない場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。
- キャンペーン規約
- 複数回応募されても当選確率は上がりません。
- 賞品発送先は日本国内のみです。
- 応募にかかる通信料・通話料などはお客様のご負担となります。
- 応募内容、方法に虚偽の記載がある場合や、当方が不正と判断した場合、応募資格を取り消します。
- 当選結果に関してのお問い合わせにはお答えすることができません。
- 賞品の指定はできません。
- 賞品の不具合・破損に関する責任は一切負いかねます。
- 本キャンペーン当選賞品を、インターネットオークションなどで第三者に転売・譲渡することは禁止しております。
- 個人情報の利用に関しましてはこちらをご覧ください。
ライブドアニュースのインタビュー特集では、役者・アーティスト・声優・YouTuberなど、さまざまなジャンルで活躍されている方々を取り上げています。
記事への感想・ご意見、お問い合わせなどは こちら までご連絡ください。
記事への感想・ご意見、お問い合わせなどは こちら までご連絡ください。